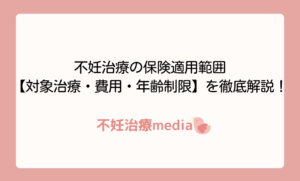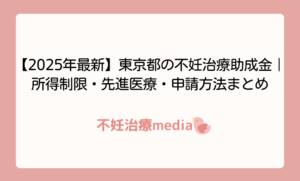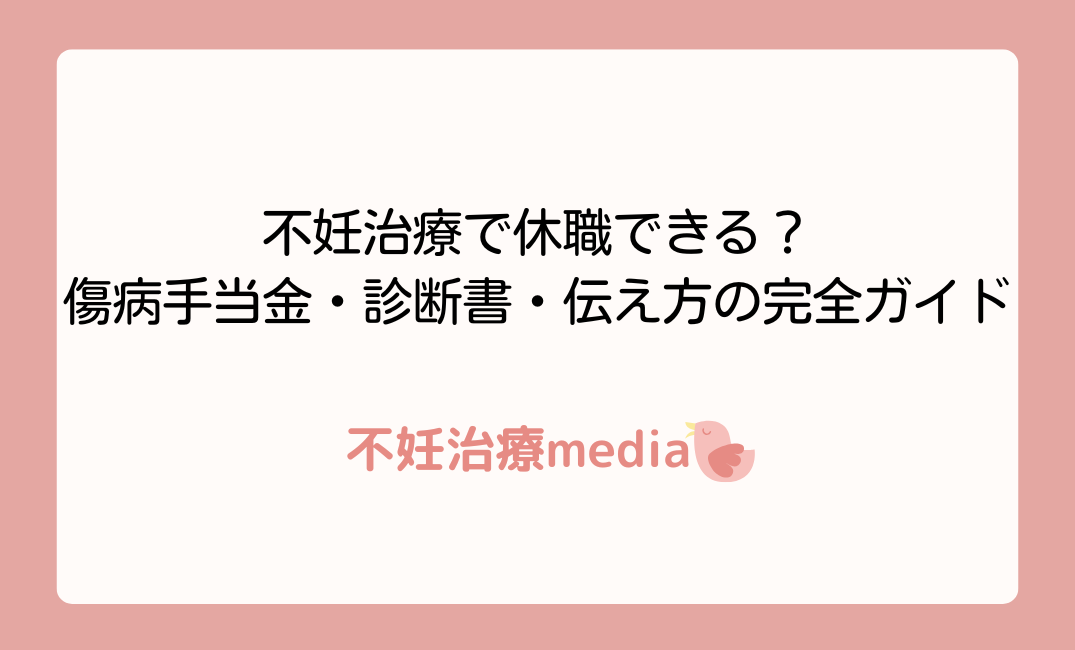
「不妊治療の通院と仕事の両立が、もう限界かもしれない…」
「キャリアも大切だけど、今は治療に専念したい。でも、どうすれば…」
あなたも今、そんな風に一人で悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、不妊治療を理由に休職することができる場合があります。 たとえ会社の制度に明記されていなくても、傷病手当金や年次有給休暇といった公的な制度や労働者の権利を活用できます。大切なのは、正しい知識を持って、適切な手順を踏むことです。
この記事を最後まで読めば、以下の3つのことが明確になります。
- 会社の就業規則に「不妊治療」の記載がなくても休職を認めてもらう方法
- 休職中の生活を支える「傷病手当金」の受給条件と具体的な申請手順
- 円満な休職を実現するための、医師への「診断書」の頼み方と会社への伝え方
社会保険労務士として、そして不妊治療の経験者として、あなたの不安な心に寄り添いながら、明日から踏み出すための一歩を具体的に解説していきます。
【Step1】まず確認すべきは会社の「就業規則」
💡このパートまとめ
就業規則に「不妊治療」の文字がなくても、「私傷病休職」の項目を確認。
不妊治療のための休職を考え始めたとき、多くの方が「うちの会社にそんな制度あるのかな?」と不安になるかと思います。その答えを知るための最初の、そして最も重要な一歩が、会社の「就業規則」を確認することです。
難しく感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば大丈夫。一緒に見ていきましょう。
就業規則のどこを見ればいい?「休職」に関する記載の探し方
就業規則は、会社のルールブックです。まずは、その中から「休職」に関する章やセクションを見つけ出してください。
注目すべきは、「私傷病(ししょうびょう)休職」という項目です。これは、業務外の病気やケガを理由に長期間仕事を休む際のルールを定めたもので、多くの場合、ここにあなたの状況に当てはまる可能性のある記述が見つかります。
具体的には、以下の点を確認してみましょう。
- 休職が認められる理由(事由):どのような場合に休職できるか。
- 休職できる期間:最大でどれくらいの期間休めるのか。
- 申請に必要な手続き:誰に、いつまでに、何を提出する必要があるか。
- 復職に関する規定:休職後、仕事に戻る際のルール。
これらの項目が、あなたの休職計画の土台となります。
「不妊治療」の記載がなくても諦めないで!私傷病休職の活用
就業規則を読んでみて、「不妊治療」という直接的な言葉が見つからなくても、決してがっかりする必要はありません。ほとんどの会社の就業規則には、不妊治療に特化した休職制度は明記されていないのが実情です。
重要なのは、先ほど触れた「私傷病休職」です。
不妊治療に伴う心身の不調は、この「私傷病」に該当すると解釈される可能性があるのです。
例えば、ホルモン治療による副作用や、頻繁な通院による精神的な負担、手術後の安静など、治療を進める上で仕事に支障が出る状態は、客観的に見ても「病気やケガの療養」に近いと言えるでしょう。
もちろん、これを会社に認めてもらうためには、医師による客観的な証明、つまり「診断書」が不可欠になります。
【Step2】休職中の生活を守る「傷病手当金」の活用法
💡このパートまとめ
傷病手当金は不妊治療でも受給可能な場合がある。医師の診断と申請が鍵。
休職を考える上で、最大の不安はやはり「収入がなくなること」ではないでしょうか。その経済的な不安を支えてくれる非常に心強い制度が、「傷病手当金」です。
これは、ご自身が加入している健康保険から支給されるもので、条件を満たせば不妊治療による休職でも受給できる可能性があります。制度を正しく理解し、賢く活用しましょう。
傷病手当金とは?4つの支給条件をチェック
傷病手当金は、誰でも自動的にもらえるわけではありません。全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトなどを参考にすると、主に以下の4つの条件をすべて満たす必要があるとされています。
- 業務外の病気やケガの療養のための休業であること
不妊治療は、業務外の療養に該当します。 - 仕事に就くことができないこと(労務不能)
これが最も重要なポイントです。自己判断ではなく、医師が「治療に伴う症状により、これまでの仕事ができない状態である」と判断・証明する必要があります。 - 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間)
休職を始めてから最初の3日間は「待期期間」とされ、傷病手当金は支給されません。4日目からが支給対象となります。この待期期間には、有給休暇や土日祝日も含まれます。 - 休業した期間について給与の支払いがないこと
休職中に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
これらの条件を満たせば、おおよそ給与の3分の2程度の額が支給されます。
不妊治療が「労務不能」と認められるには?
4つの条件の中で、特に解釈が難しいのが「労務不能」という点です。
「不妊治療」という名前だけでは、病気やケガとは少し違う印象を持たれるかもしれません。
ここで重要なのは、申請理由が「不妊治療のため」というだけでなく、「治療に伴う心身の症状により、これまでの仕事ができない状態である」という医学的な証明です。
例えば、以下のような状態が考えられます。
- ホルモン剤の副作用による重い頭痛、吐き気、めまい、倦怠感で、デスクワークや立ち仕事が困難。
- 頻繁な通院が必要で、定時勤務が物理的に不可能。
- 採卵手術や胚移植手術後、医師から一定期間の安静を指示されている。
- 治療による精神的ストレスが大きく、抑うつ状態で業務に集中できない。
これらの状態を、申請書の医師記入欄に具体的に書いてもらうことが、スムーズな受給への鍵となります。
傷病手当金の申請フローと必要書類
傷病手当金の申請は、ご自身で書類を準備し、会社や医療機関に協力を依頼する必要があります。一般的な流れは以下の通りです。
- 申請書の入手:ご自身が加入する健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトから「傷病手当金支給申請書」をダウンロードするか、会社の担当部署に依頼して入手します。
- 本人記入欄の作成:ご自身の情報や振込先口座などを記入します。
- 会社への依頼:会社の担当部署に、休職期間中の勤務状況や給与支払いに関する証明欄を記入してもらいます。
- 医療機関への依頼:通院しているクリニックに、療養を担当した医師としての意見欄を記入してもらいます。
- 提出:すべての記入が完了したら、ご自身で健康保険組合や協会けんぽの窓口に提出します。
【Step3】円満な休職を実現する「診断書」と「会社への伝え方」
💡このパートまとめ
医師に「労務不能」と記載依頼。会社には具体的な配慮を冷静に伝える。
制度の知識が揃っても、実際に休職を実現するためには「医師からの診断書」と「会社への円滑なコミュニケーション」という、実務的かつ心理的なハードルを越える必要があります。
ここは多くの方がつまずきやすいポイントですが、少しのコツで乗り越えられます。
医師への「診断書」依頼のポイント
会社に休職を申請する際、多くの場合、その理由を証明するための「診断書」の提出を求められます。これは、あなたの休職が正当なものであることを会社に理解してもらうための重要な書類です。
依頼する際のポイントは以下の通りです。
- タイミング:休職の意向を固め、上司などへ相談する目途が立った段階で、主治医に相談するのがスムーズです。
- 依頼内容:単に「不妊治療のため」だけでなく、「不妊症の治療加療のため、〇年〇月〇日から約〇ヶ月間の休養および労務不能の状態と判断する」といったように、具体的な休養期間と、仕事ができない状態であるという文言を入れてもらうよう、丁寧にお願いしましょう。傷病手当金の申請も考えている旨を伝えると、医師も状況を理解しやすくなります。
- 傷病手当金申請書との連携:傷病手当金を申請する場合は、診断書とは別に、申請書内の医師記入欄への記入も必要になります。二度手間にならないよう、同時に依頼できるか確認するとよいでしょう。
上司・人事への伝え方【例文付き】
会社に不妊治療のことを伝えるのは、非常に勇気がいることだと思います。誰に、いつ、どこまで話すか、悩んでしまいますよね。
まず相談する相手は、直属の上司が第一候補です。そして、伝えるべきは感情的な辛さだけでなく、「治療に専念したいという意志」と、「そのために必要な配慮(休職期間など)」、そして「業務の引き継ぎは責任を持って行うという姿勢」をセットで伝えることが、円満な合意への近道です。
【伝え方の例文】
「〇〇部長、今、少しよろしいでしょうか。
実は、個人的なことで大変恐縮なのですが、現在、不妊治療を行っております。
これまでは仕事と両立させてきたのですが、治療が本格化し、一度治療に専念させていただきたいと考えております。
つきましては、会社の休職制度を利用させていただきたく、ご相談に上がりました。
期間としては、医師とも相談し、〇ヶ月ほどを考えております。
業務の引き継ぎにつきましては、ご迷惑をおかけしないよう、責任を持って行いますので、ご検討いただけますでしょうか。」
このように、具体的な要望と、会社への配慮を合わせて伝えることが大切です。
「不妊治療連絡カード」を活用しよう
どうしても口頭で説明するのが難しい、あるいは何を伝えればいいか分からない、という方には、厚生労働省が作成した「不妊治療連絡カード」の活用をお勧めします。
これは、治療内容や必要な配慮(通院日、安静期間、体調など)を医師に記入してもらい、それを会社に提出することで、円滑なコミュニケーションを支援するツールです。
診断書と合わせて活用することで、より客観的に、かつ具体的にご自身の状況を伝えることができます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30b.pdf
会社の制度がない・休職が難しい場合の選択肢
💡このパートまとめ
会社の制度がなくても、年休や休暇制度の活用が可能。不利益取扱いは違法。
「就業規則を確認したけれど、休職制度そのものがない」「休職は少しハードルが高い…」という場合でも、諦める必要はありません。
いくつかの代替案を検討してみましょう。
まずは「年次有給休暇」の計画的利用
まず考えられるのは、労働者に与えられた権利である年次有給休暇(年休)の活用です。
採卵日や移植日など、ピンポイントで休みが必要な日に合わせて計画的に取得することで、仕事を継続できる場合もあります。
また、会社によっては1日単位だけでなく、半日単位や時間単位で年休を取得できる「時間単位年休」制度を導入している場合もあります。通院が数時間で済む場合などには、非常に有効な選択肢となります。
会社独自の「病気休暇」「特別休暇」の確認
年次有給休暇とは別に、会社独自の休暇制度が利用できる可能性もあります。
- 病気休暇:年休とは別に、病気療養のために設けられた休暇制度。有給の場合と無給の場合があります。
- 特別休暇:慶弔休暇などが有名ですが、企業によっては「不妊治療休暇」「ファミリーサポート休暇」といった名称で、不妊治療に利用できる独自の休暇制度を設けている場合があります。
もう一度、就業規則を丁寧に確認したり、人事部に問い合わせてみましょう。
知っておきたい法的知識:不利益取扱いの禁止
ここで、あなたを守るための大切な法律の知識をお伝えします。
厚生労働省は、男女雇用機会均等法に基づく指針の中で、事業主が不妊治療を理由として、労働者に対して解雇や降格、減給などの不利益な取扱いを行うことは望ましくない、としています。
もし、会社に相談した結果、心ない言葉を言われたり、不利益な扱いを受けたりした場合には、一人で悩まずに、各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)などの専門機関に相談してください。あなたには、安心して治療を受ける権利があります。
Q&A:不妊治療と休職に関するよくある質問
💡このパートまとめ
公務員や男性のケース、復職の不安など、具体的な疑問に回答。
このセクションでは、これまで解説しきれなかった、不妊治療と休職に関する具体的な質問にお答えします。
- 公務員の場合、制度は違いますか?
-
はい、公務員の方は、一般企業とは異なる手厚い制度が設けられていることが多いです。国家公務員の場合、人事院の規則に基づき、不妊治療のために「病気休暇」(最大90日)や、それとは別に「特別休暇(不妊治療休暇)」(年間5日、体外受精等に関わる場合はさらに5日追加可)を取得できると定められています。地方公務員の方も、多くは各自治体の条例で同様の制度が整備されています。詳しくは、所属先の人事担当部署や共済組合にご確認ください。
- パートナー(男性)が休みを取得できる制度はありますか?
-
もちろんです。パートナー(男性)も、通院の付き添いや説明会への参加などのために、年次有給休暇を取得することは労働者の権利として認められています。また、企業によっては「配偶者の不妊治療サポート休暇」といった独自の制度を設けているケースも増えています。さらに、精子の採取や検査などでご本人が休む必要がある場合は、女性と同様に私傷病として扱われ、病気休暇などが利用できる可能性があります。まずは会社の制度を確認してみましょう。
- 休職後の復職が不安です…
-
休職期間が長くなると、復職への不安を感じるのはとても自然なことです。その不安を少しでも和らげるために、休職に入る前に、復職までの大まかなプロセスを会社と話し合っておくことをお勧めします。例えば、「復職の1ヶ月前を目処に、医師の診断書を基に面談を実施する」「最初の1週間は短時間勤務から始めさせてもらう」といった具体的な見通しを立てておくと、心の準備ができます。また、休職中もメールなどで簡単な近況報告をするなど、会社との接点を完全に断たないようにすると、スムーズな復帰に繋がりやすいでしょう。
まとめ:一人で悩まず、制度を知って、まず一歩を踏み出そう
💡このパートまとめ
あなたは一人ではない。会社の制度、国の制度を正しく知り、専門家や会社、医師に相談することから始めよう。
ここまで、不妊治療と仕事の両立、特に休職に関する制度や手続きについて詳しく解説してきました。
情報量が多く、少し大変に感じられたかもしれません。
しかし、最もお伝えしたいのは、「不妊治療のために休むことは、特別なことでも、わがままなことでもない」ということです。あなたの心と体を守り、安心して治療に専念するためには、利用できる制度を正しく知り、適切に活用する権利があります。
【今日のまとめ】明日からできる3つのステップ
- 調べる: まずはご自身の会社の「就業規則」を取り寄せ、「私傷病休職」の項目を読んでみましょう。
- 相談する: 次の診察日に、主治医に「休職も考えている」と伝え、「診断書」や「傷病手当金」について相談してみましょう。
- 伝える: 専門家やこの記事を参考に、会社への「伝え方」をシミュレーションしてみましょう。
一人で抱え込まず、頼れる制度や人を最大限に活用してください。この記事が、あなたの重荷を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すための勇気となることを、心から願っています。
【免責事項】
本記事に掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の状況に対する法的助言や診断に代わるものではありません。具体的な対応については、必ず会社の担当部署、医師、または社会保険労務士等の専門家にご相談ください。