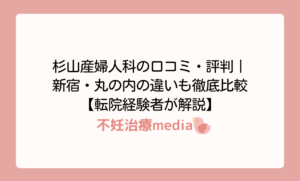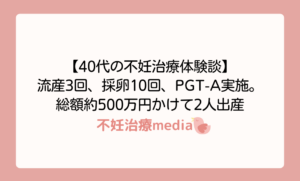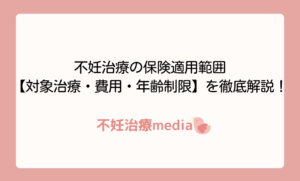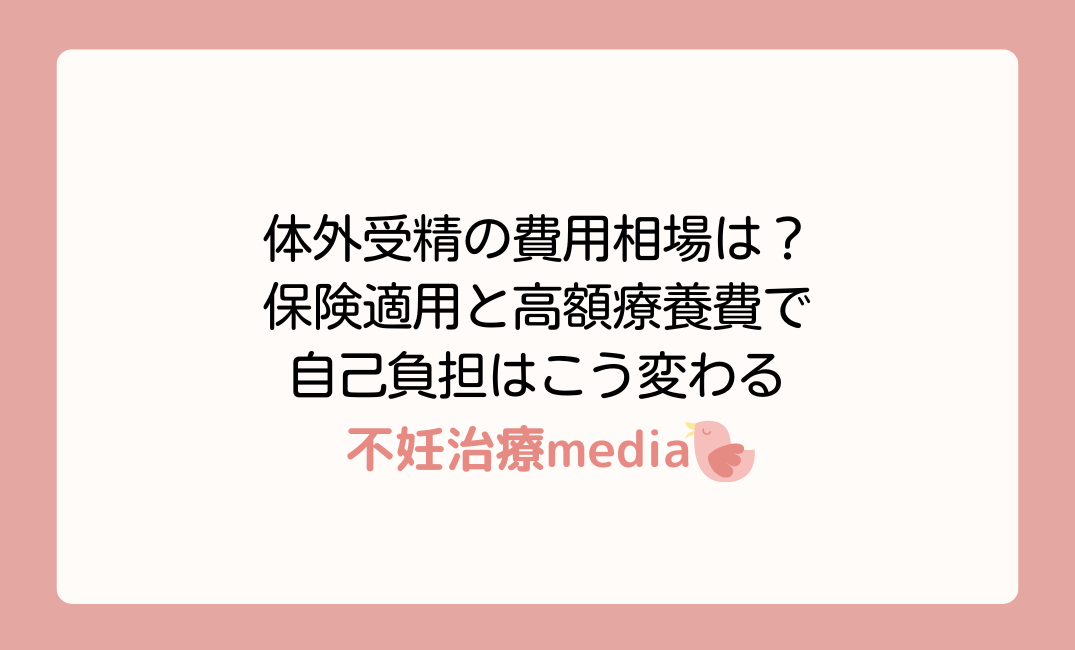
医師から体外受精を勧められたものの、費用がいくらかかるのか見当もつかず、ご夫婦での話し合いが進まない…。そんな切実な悩みを抱えていらっしゃる方もいるでしょう。
結論からお伝えします。保険適用後の体外受精の費用相場は、1周期あたり約15万~40万円ですが、さらに「高額療養費制度」を活用すれば、最終的な自己負担額は月8~9万円程度に抑えられるケースがほとんどです。 制度を正しく理解し、賢く活用することが、経済的な不安を解消する鍵となります。
この記事を最後まで読めば、以下の3つのことがスッキリと分かります。
- 保険適用後の体外受精、治療ステージごとのリアルな費用相場
- あなたの年収ならいくら戻る?高額療養費制度の具体的な計算方法
- 先進医療や助成金まで含めた、最終的な費用総額の考え方
体外受精の費用、相場の「内訳」を知ろう【ステージ別】
👉この章のまとめ
体外受精の費用相場は主に「採卵周期」と「移植周期」の2段階で発生します。
「体外受精の費用」と一言で言っても、治療はいくつかの段階に分かれており、それぞれに費用が発生します。まずは、お金の全体像を掴むために、費用相場の主な内訳を見ていきましょう。
費用が発生するタイミングは、大きく分けて「採卵周期」と「胚移植周期」の2つのステージです。
【ステージ1】採卵周期の費用相場(診察・採卵・培養など)
採卵周期は、卵子を育てて体外に取り出し、受精させて凍結するまでの一連のプロセスです。最も費用がかかるステージであり、保険適用(3割負担)の場合でも、自己負担額の相場は約15万円~30万円程度となります。
| 費目 | 金額(相場) | 備考 |
|---|---|---|
| 診察・検査費 | 2~5万円 | ホルモン値測定、超音波検査など |
| 排卵誘発の薬剤費 | 2~8万円 | 注射薬の種類や量で大きく変動 |
| 採卵手術費用 | 約7.2万円 | |
| 顕微授精費用 | 約4.8万円 | 実施した場合 |
| 胚培養・凍結費用 | 約4.5万円~ | 培養・凍結する個数で変動 |
| 合計 | 約15~30万円 |
【ステージ2】胚移植周期の費用相場(診察・移植・薬剤など)
採卵周期で凍結した受精卵(胚)を、子宮内に戻すのが胚移植周期です。こちらは採卵周期に比べると費用は抑えられ、自己負担額の相場は約3万円~10万円程度です。主な内訳は、診察費、凍結胚の融解費用、移植手技料、移植後の薬剤費などです。
【基本】費用相場を左右する「保険適用」のルール
👉この章のまとめ
体外受精の基本治療が3割負担に。ただし年齢・回数制限に注意が必要。
2022年4月から、高額だった体外受精が保険適用の対象となり、経済的な負担が大きく軽減されました。この基本的なルールを理解しておくことが、費用計画の第一歩です。
保険適用される治療の範囲
厚生労働省の定めにより、現在では体外受精における基本的な治療のほとんどが保険でカバーされ、自己負担3割で受けられるようになっています。
具体的には、これまで解説してきた採卵、顕微授精、受精卵(胚)の培養、胚凍結、胚移植といった一連のプロセスが対象です。
ただし、後述する「先進医療」など、一部保険適用外となる治療もあります。
知っておくべき年齢・回数制限
この保険適用には、公平性の観点から年齢と治療回数に上限が設けられています。ご自身の状況が当てはまるか、必ず確認してください。
- 年齢制限: 治療を開始した時点での女性の年齢が43歳未満であること。
- 回数制限: 保険適用で胚移植を行える回数は、40歳未満であれば通算6回まで、40歳以上43歳未満であれば通算3回までとなっています。
| 治療開始時の女性の年齢 | 保険適用される胚移植の回数 |
|---|---|
| 40歳未満 | 通算6回まで |
| 40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
| 43歳以上 | 対象外 |
【この記事の核心】「高額療養費制度」で最終的な自己負担額が決まる!
👉この章のまとめ
高額療養費制度で、月の自己負担額に上限を設定。年収別に解説。
さて、ここからがこの記事で最もお伝えしたい、あなたの負担を劇的に軽くする最重要ポイントです。それが「高額療養費制度」です。
保険適用で3割負担になったとしても、採卵周期では20万円を超えることもあります。しかし、この制度を使えば、月の自己負担額に上限が設けられ、それを超えた分は後から払い戻されるのです。
あなたの味方、「高額療養費制度」の仕組みとは?
高額療養費制度とは、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額(保険適用分のみ)が、年齢や所得によって決まる上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
この上限額は、ご自身が加入している健康保険(協会けんぽ、企業の健保組合など)に申請することで、診療月からおよそ3~4ヶ月後に払い戻されます。
✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス
【結論】: 高額療養費制度は、自動で適用されるわけではありません。さらに、多くの人が知らない『世帯合算』や『多数回該当』という仕組みを理解すれば、負担をさらに軽減できる可能性があります。
あなたの自己負担上限額はいくら?年収別の限度額 早見表
自己負担の上限額は、あなたの所得によって決まります。まずは、以下の表でご自身の年収がどの区分に当てはまるか、確認してみてください。
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 年収の目安 | 1ヶ月の上限額(自己負担限度額) |
|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 約1,160万円~ | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% |
| イ | 53万~79万円 | 約770万~約1,160万円 | 167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 28万~50万円 | 約370万~約770万円 | 80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% |
| エ | 26万円以下 | ~約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税者 | – | 35,400円 |
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
【年収500万円の例】費用相場はどう変わる?徹底シミュレーション
では、最も多くの方が当てはまるであろう「区分ウ(年収約370万~約770万円)」のケースで、実際にいくら戻ってくるのか計算してみましょう。
【条件】
- あなたの年収:500万円(区分ウ)
- 採卵周期にかかった医療費総額:67万円
- あなたが窓口で支払った3割負担額:約20万円
【計算】
区分ウの自己負担限度額の計算式は「80,100円 + (総医療費-267,000円)×1%」です。
これに当てはめると、
80,100円 + (670,000円 – 267,000円) × 1% = 84,130円
あなたのこの月の上限額は84,130円となります。
【結論】
あなたは窓口で20万円支払いましたが、上限額は84,130円なので、
200,000円 – 84,130円 = 115,870円
この約11.6万円が、後日あなたの口座に払い戻されるのです。
先進医療・助成金も考慮した「総額」の考え方
👉この章のまとめ
先進医療は全額自己負担だが、自治体の助成金でカバーできる場合も。
基本的な治療は保険適用と高額療養費制度で大きくカバーできることが分かりました。
しかし、「先進医療」を追加した場合や、さらなる負担軽減策についてもお伝えします。
「先進医療」を追加した場合の費用相場
PGT-A(着床前診断)など、より高度な「先進医療」は保険適用外となり、全額が自己負担です。
これを選択した場合、治療費総額はこれまで見てきた金額に、先進医療の費用(数十万円単位になることも)が上乗せされる形になります。
自治体の「助成金」をチェックしよう
この先進医療の費用負担を軽減するために、多くの自治体が独自の助成金制度を設けています。
例えば、東京都では先進医療にかかった費用の10分の7(上限15万円)が助成されます。
※ただし、1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。全額自費で先進医療を実施した場合は、対象となりませんのでご注意ください。
お住まいの自治体のウェブサイトで、「〇〇市 不妊治療 助成金」と検索し、利用できる制度がないか必ず確認しましょう。
Q&A:体外受精の費用相場に関するよくある質問
- 40代の体外受精費用は、30代と比べて相場は高くなりますか?
-
1回あたりの治療費相場そのものは年齢で変わりませんが、一般的に40代は治療回数が多くなる傾向があるため、結果として総額が高くなる可能性があります。特に、保険適用での胚移植が3回までとなるため、高額療養費制度の活用はもちろん、助成金や後述する医療費控除まで含めた、より戦略的な資金計画が重要になります。
- 助成金はどの自治体でももらえますか?
-
いいえ、助成金制度の有無や内容は、お住まいの自治体によって大きく異なります。先進医療のみを対象とする自治体、所得制限がある自治体、または制度自体がない場合もあります。必ず「〇〇市 不妊治療 助成」など、ご自身の市区町村名を入れて検索し、公式サイトで最新の情報を確認してください。
まとめ:費用相場を正しく理解して、安心して治療への一歩を
👉この章のまとめ
体外受精の費用は公的支援で大きく軽減可能。まずはあなたの限度額確認から。
体外受精の費用相場は、一見すると非常に高額で、治療をためらう大きな壁に感じられるかもしれません。
しかし、ここまで見てきたように、①保険適用 と ②高額療養費制度 という2つの強力な公的支援を組み合わせることで、あなたの自己負担は大きく抑えられます。
あなたの家計にとって最も重要なのは、ご自身の所得区分での「自己負担限度額」を事前に把握しておくことです。それが、あなたの心の安心材料になります。

不妊治療の領収書は、「高額療養費の申請用」と、年末の「医療費控除の申請用」の2つの目的で必要になります。治療開始と同時に、専用のファイルを作って月別に整理しておくことが、後々の手間を劇的に減らす最大のコツです。
【免責事項】
本記事に掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の状況に対する税務・法務上の助言や診断に代わるものではありません。最新の制度や料率については、必ずご加入の健康保険組合や厚生労働省の公式サイトをご確認ください。